前編ではチケットをもとに、ざっくりと中国の列車の種別、座席などを紹介しましたが、今回は線路、運行システム、乗車体験について紹介します。この紹介を通じて、直通運転や改札などに関する情報を中国の観光客にどう伝えたらいいのかなどの悩みに一助になれたらうれしいです。
路線図
中国は、総延長15万キロメートルを超える鉄道網を有しており、全国のほぼすべての地域に鉄道が通じています。そのうち、約4万キロメートルは高速鉄道が占めており、世界でも類を見ない規模を誇ります。
なお、中国の高速鉄道と在来線は、いずれも標準軌(1,435mm)を採用しているものの、運行システムや駅の設備、ダイヤの設計などが大きく異なるため、基本的には直通運転が行われていません。
本稿では、この広大な鉄道網のうち、高速鉄道に限定して路線図をご紹介いたします。その理由として、高速鉄道は建設時に高度な土木技術が用いられており、山岳地帯や河川といった自然条件に左右されにくく、効率的なルート設計が可能となっている点が挙げられます。
このような背景から、高速鉄道の路線図のほうが、現代中国における都市間の実質的なつながりをより的確に反映していると考えています。
四縦四横
なお、中国の高速鉄道網は、計画的かつ戦略的に整備が進められており、その骨格を成すのが、いわゆる「四縦四横」と呼ばれる高速鉄道幹線網です。
「四縦」とは、南北方向に走る4本の幹線ルートを指し、以下のような主要都市を結んでいます:
- 北京〜上海線:首都北京と経済の中心地・上海を結ぶ最重要路線
- 北京〜広州線:南方の経済圏と北方を結ぶ大動脈
- 北京〜哈爾浜(ハルビン)線:東北地域の中心都市と首都を直結
- 上海〜深圳線:中国の東部と南部を縦断し、沿海部を連携
一方の「四横」は、東西方向の4本の幹線で、以下のような都市間を高速で連絡しています:
- 青島〜太原線:黄河の河口である山東半島と内陸部を東西に結ぶ
- 徐州〜蘭州〜ウルムチ線:華中と西南部を連絡
- 上海〜成都線:長江に沿って上海から西部内陸の経済圏へ
- 上海〜昆明線:華東地域から南西部の雲南省までを網羅

この「四縦四横」の整備により、中国全土の主要都市間において、8時間以内で移動できる高速鉄道ネットワークが構築されつつあります。この構想は後に「八縦八横」へと拡張され、より広域かつ高密度な移動インフラへと発展していますが、まずは「四縦四横」が、その基礎を築いた重要なステップと言えるでしょう。
運行主体
国鉄
中国の高速鉄道網の建設・運営を一元的に担っているのが、中国国家鉄路集団有限公司(略称:国鉄集団)です。2019年に旧・中国鉄路総公司から法人化され、中央政府直属の国有独資企業として設立されました。
同社は、中国全土に広がる鉄道ネットワークの運行管理、インフラ整備、旅客サービスを統括しており、高速鉄道を含む全国規模の鉄道計画を実行に移す中核機関となっています。
鉄路局
中国国家鉄路集団の下には、各地域を管轄する鉄路局(鉄路局公司)が配置されており、全国を約18のエリアに分けて運営が行われています。例えば、「北京鉄路局」「上海鉄路局」などがこれに該当します。
これらの地域鉄路局は、それぞれのエリアにおける以下の業務を担っています:
- 列車運行の現地管理(運行ダイヤの実施、列車の運用計画)
- 駅や車両の保守・運営
- 地域内でのサービス品質の管理
- 輸送実績・収支の管理
国家鉄路集団が全体戦略や投資計画を策定する「本社機能」であるのに対し、地域鉄路局は、その戦略を現場で実行する「運用部隊」として機能しています。この分業体制により、中国全土にわたる広大な鉄道ネットワークにおいても、統一された品質と高い効率での運行が実現されています。

実際には利用者が意識する必要はほとんどない
前述の通り、中国には18の地域鉄路局が存在しますが、チケット購入や乗車手続き、運行情報の取得など、利用者の目に触れる部分は基本的に全国で統一されています。
たとえば:
- チケット予約は12306(公式サイトまたはアプリ)に一元化されており、発券・変更・払い戻しの手続きも全国共通です。
- 駅構内の構造や案内サインも、国家鉄路集団のガイドラインに沿って標準化されています。
- 鉄道車両や座席の仕様、車内サービスも同じ基準で提供されており、地域ごとの差異はほとんど感じられません。
そのため、鉄道利用者が「この列車はどの鉄路局の運行か」「この駅はどの局の管轄か」といった点を意識する場面は、実務上は極めて限られます。
一部で設備や案内対応に「地域差」が見られることもありますが、それはあくまで現地の状況や予算差によるもので、鉄路局単位で特別に気を付けるべき点はありません。
運賃
料金については各鉄路局が管内の線路の料金を決めることができる仕組みとなっています。基本どこも大して変わりませんが、広州局管内のエリアだけ他の地方の1.5倍から2倍ぐらい高くなっています。中国の鉄道ファンからは「抢铁(QiangTie)」(お金を奪う鉄道)と愛称がつけられています。
直通運転はあるのか
中国の鉄道にも、「直通運転」に相当する運行形態は存在しますが、その意味合いと運用のされ方は日本とはやや異なります。
同一会社内での「路線またぎ直通」
中国の鉄道網は基本的に中国国家鉄路集団の単一システムで構築されており、日本のように運営会社ごとに路線が分かれているわけではありません。そのため、北京発・上海着の高速鉄道が複数の鉄路局をまたいで走行するような「長距離運行」は日常的で、利用者から見ると“直通”というより“全線通し運転”が当たり前という状況です。
そしてこの“全線通し運転”が基本であるため、中国の鉄道駅は日本のようなXX線専用のホームという概念がなく(一部にはあるが)、すべてのホームからすべての線路へとまたぐことが可能です。そのため、乗り間違いを防止するために、ホームごとに改札機が設けられ、発車直前に改札が行われる仕組みになっています。飛行機の搭乗口のような役割を果たしています。
チケット販売システムーー12306
中国の鉄道予約システム「12306」は、中国鉄道の公式チケット予約サイト及びアプリであり、鉄道チケットの予約、購入、変更、払い戻しを行うための一元管理システムです。このシステムは、全国どこでも、どの路線でも利用可能であり、非常に便利で効率的です。詳細の使い方はほかのところでたくさん紹介されているので、割愛させていただきます。ここでは12306についての豆知識をいくつか紹介します。
チケットの購入
中国の鉄道のチケットシステムをすでに紹介しており、基本航空券を買うのと一緒なイメージです。列車・座席を指定しての購入となり、無座でも指定された列車にしか乗車できません。発売が15日前からとなっており、変更・払い戻しには手数料を近年とるようになりました。
チケットの発売
基本ルール:オンラインからは通常乗車日の15日前の午前7時(北京時間)から始まります。これはオンライン(12306公式サイト・アプリ)および電話予約に共通しています。駅の窓口や券売機でのチケット発売は、オンライン予約より1日遅れのため、14日前からとなるのが通例です。したがって、人気路線や混雑期は、オンライン予約がほぼ必須となります。
例外として、春節(旧正月)、国慶節(日本で言う建国記念日)などの需要の集中が見込まれる時期には、発売時期が早くなることがあります。
さらに、すべての列車が午前7時に一斉に発売されるわけではなく、路線や発着駅によって「販売開始時刻」が段階的に設定されています(7時~18時の間で時差あり)。
長距離区間の優先発売
中国の一番旅客需要がある時期と言えば、春節です。春節では労働者が一斉に経済が発達している東部・南部の沿海部から内陸部へと帰ります。そして春節が終わったらまた労働者たちは沿海部へ出稼ぎに行きます。この数十億にも上る旅客需要を混乱なくさばけるように中国の鉄道は「長距離優先」の運転・販売体系となっています。一例として、「北京南 始発〜上海虹橋 終着」の運用があった場合:
- 発売開始時点では、北京南~上海虹橋間を通しで利用する乗客向けに座席が開放されます。
- 時間が経ち、長距離区間の需要が一定以下になると、中・短距離の乗車区間にも空席が開放されます。
- 途中の「済南西」「南京南」などの中間駅で部分的に乗車・下車する乗客用の座席は、初期段階では制限される傾向があります。
- 区間ごとの残席数、さらに短距離区間がいつ開放されるかなどの情報が利用者側に公開されません。
このため、短距離の利用者が繁忙期において、わざと乗る予定の区間より長い区間を購入し、座席を確保する裏技が開発されています。(チケットの区間を途中乗車・途中下車することができる)
まとめ:中国鉄道システムの全体像とその特徴販売
中国の鉄道は、全国を網羅する高速鉄道網「四縦四横」を基盤に、国家レベルで統一管理されています。運行はすべて中国国家鉄路集団が担い、チケット購入や駅設備、車内サービスも全国でほぼ共通。利用者にとっては非常に分かりやすい仕組みです。
直通運転の概念は日本とは異なり、長距離の通し運転が主流で、駅の改札方式も独自です。また、チケットは「12306」で予約するのが基本で、長距離優先の販売ルールもあります。
こうした背景を理解することで、訪日中国人観光客に対して日本の鉄道事情を説明する際も、どの部分が共通し、どこが異なるのかを適切に伝えることが可能になります。国ごとの「当たり前」の違いを踏まえたうえで、より円滑な情報提供や接遇に役立てていただければ幸いです。

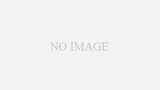
コメント